はじめに

毎日職場に行くのが辛くて…。ADHDの診断を受けてから、今の環境が自分に全く合っていないことがよくわかったんです。でも、どんな職場なら働きやすいのかがわからなくて。

私自身も同じことで、職場環境の重要性を身をもって感じてきました。実は、ADHDの人が働きやすい職場には共通する特徴があるんです。今日は、私の経験と多くの当事者の声をもとに、その特徴を5つに絞ってお話しします。
「今の職場、どうしてこんなにしんどいんだろう?」—— そんな疑問を抱えているADHDの方は決して少なくありません。毎朝起きるのが億劫で、職場に向かう足取りが重く、一日が終わる頃にはぐったりと疲れ果てている。そんな日々が続いていませんか?
ADHDの人にとって、職場環境との相性は想像以上に重要です。同じ人でも、環境が変わるだけでパフォーマンスが劇的に向上することは珍しくありません。
逆に、特性に合わない環境では、どんなに頑張っても能力を発揮できず、自信を失ってしまうこともあります。
この記事では、ADHDの特性に合う「働きやすい職場の特徴」を5つに絞って、具体的に解説していきます。
これらの特徴を知ることで、転職活動の指針になったり、現在の職場環境を改善するためのヒントを見つけたりできるはずです。
またADHDの基本特性について知りたい方は以下の記事もご覧ください
現在、働いているが「本当にやりたいことが分からない」「自分はこの仕事に適しているのだろうか」と悩んでいる人も多いと思います。
そのような人は「ココシロ!適職診断![]() 」を受けてみましょう。
」を受けてみましょう。
ココシロ!適職診断![]() は簡単な30個の質問に答えるだけで、あなたの強みや仕事の適正もスグにわかる完全無料の診断サイトです。
は簡単な30個の質問に答えるだけで、あなたの強みや仕事の適正もスグにわかる完全無料の診断サイトです。
最短3分で、あなたの性格や価値観、適職タイプなど一目でわかります。
ADHDの人は自己理解が低く、自分の働き方やキャリアの選択を間違えている場合も多いので、一度利用されることをお勧めします。
詳細は以下よりご覧ください。
①フレキシブルな勤務体制(在宅・フレックスなど)

現代の働き方改革や新型コロナウイルス蔓延により注目が集まる柔軟な勤務制度は、ADHDの特性にとって特に大きなメリットをもたらします。

在宅ワークやフレックスって、ADHDの人にとってそんなにメリットがあるんですか?逆に、家だと集中できないんじゃないかって心配で…。

確かにその心配はよくわかります。でも、適切な環境を整えれば、在宅ワークはADHDの人にとって非常に魅力的な働き方になるんです。あることを意識すれば実際に私も在宅ワークを始めてから、生産性が格段に上がりました。
在宅ワークのメリット
外部刺激を最小限にできる
ADHDの脳は、周囲の刺激に敏感に反応します。オフィスでの電話の音、同僚の話し声、足音、エアコンの音など、一般的な人には気にならない刺激も、ADHDの人にとっては集中力を削ぐ大きな要因となります。
在宅ワークなら、これらの刺激をコントロールできます。必要に応じてノイズキャンセリングイヤホンを使ったり、自分の好みの音楽やブラウンノイズノイズを流したりすることで、理想的な音環境を作れます。
ブラウンノイズについての説明記事はこちら👇
自分が集中しやすい環境を整えられる
デスクの配置、照明の明るさ、室温、香り——これらすべてを自分の好みに調整できることは、ADHDの人にとって計り知れないメリットです。
例えば、私の場合は以下のような工夫をしています
通勤ストレスからの解放
朝の準備、満員電車、時間に追われる焦り——これらのストレスは、一日の始まりからエネルギーを大幅に消耗させます。
在宅ワークにより、このストレスがなくなるだけで、本来の業務に集中できるエネルギーを大幅に温存できます。
フレックスタイムの魅力

フレックスタイムも気になるんですが、朝起きるのがすごく苦手で…。これってADHDあるあるですか?

まさにそうです!多くのADHDの人が朝型ではなく、むしろ午後から夜にかけて調子が上がる傾向があります。フレックスタイムは、この特性を活かす絶好の制度なんです。
朝が苦手でもOK
ADHDの人の多くは、概日リズム(体内時計)が一般的な人とは異なります。夜型の傾向が強く、朝早く起きることに大きなストレスを感じる人が少なくありません。
フレックスタイム制度があれば、自分の生体リズムに合わせて出社時間を調整できます。午前10時や11時から始業することで、無理なく一日をスタートできます。
自分のリズムで働けることでストレス軽減
ADHDの人は、集中力の波があります。午前中は頭がぼんやりしていても、午後になると急に集中力が高まることも珍しくありません。
フレックスタイムなら、自分の集中力が高まる時間帯に重要な業務を行い、調子の上がらない時間帯は軽めの作業に充てるといった調整が可能になります。
ADHDのタスク処理に関する紹介記事はこちら👇
② 静かで外からの刺激が少ない環境

ADHDの特性である「感覚過敏」を理解し、正しく働く環境を整えることで、集中力を大幅に向上させることができます。

今のオフィスがオープンスペースで、周りの音や動きが気になって全然集中できないんです。こういう環境って、ADHDの人には向いていないんでしょうか?

まさにその通りです。オープンオフィスは一般的には協調性やコミュニケーションを促進すると言われていますが、ADHDの人にとっては集中の大敵になることが多いんです。理想的な働く環境について具体的に説明しますね。
オフィスにおける働き方について
仕切りのあるデスクや個室を活用
視覚的な刺激をコントロールできることは、ADHDの人にとって非常に重要です。
たとえば隣の席の人の動きや、通りすがる人の影が視界に入るだけで、集中が途切れてしまうことがあります。
| 理想的な環境 |
|
整理整頓されたデスク周り
ADHDの人は、視覚的な情報に敏感です。
デスク周りや視界に入る範囲がごちゃごちゃしていると、無意識のうちに注意が散漫になってしまいます。
| 工夫すること |
|
ツールの活用
ノイズキャンセリングイヤホンの活用
周囲の音をシャットアウトできるノイズキャンセリングイヤホンは、ADHDの人にとって必須アイテムの一つです。完全に無音にするだけでなく、集中力を高める音楽やホワイトノイズを流すことで、より効果的に集中できます。
| おすすめの音環境 |
|
ポモドーロタイマーで時間管理
ADHDの人は時間感覚が独特で、気がついたら時間が過ぎていたり、逆に時間が経っていないように感じたりします。ポモドーロテクニック(25分作業+5分休憩のサイクル)を活用することで、集中力を持続させやすくなります。
| デジタルツールの活用 |
|
③明確な指示・優先順位づけの方法
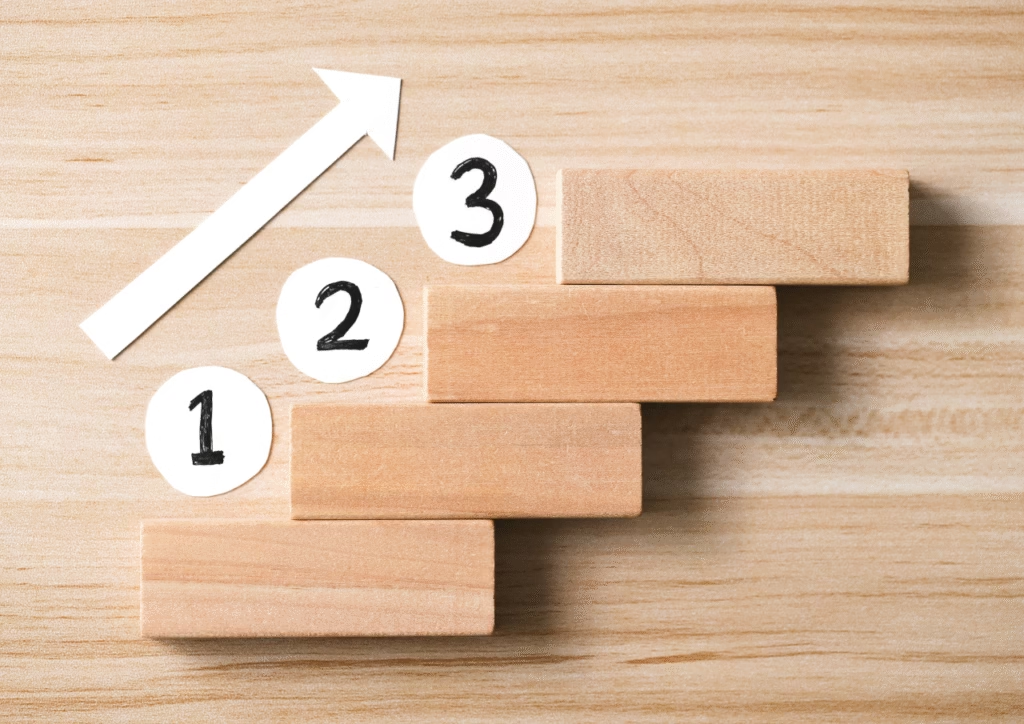
曖昧な指示はADHDの人にとって大きなストレス源です。具体的で明文化された指示があることで、能力を十分に発揮できます。

上司から「適当によろしく」とか「いい感じに」って言われることが多くて、何をどこまでやればいいのかわからなくて混乱してしまうんです。

それはADHDの人が最も苦手とする指示の出し方ですね。私も同じような経験があります。曖昧な指示は、ADHDの脳にとって処理が非常に困難なんです。理想的な指示の出し方について説明します。
ADHDにありがちな困りごと
曖昧な指示に混乱
「きれいに作って」「早めに対応して」「しっかりやって」——このような抽象的な指示は、ADHDの人にとって処理が困難です。何をもって「きれい」なのか、「早め」とはいつまでなのか、「しっかり」の基準は何なのかが明確でないためです。
この曖昧さにより、以下のような問題が生じます
どれから手をつけていいかわからない
複数の業務を同時に抱えている時、すべてが同じくらい重要に見えてしまい、優先順位をつけることができません。結果として、締切の近いものから手当たり次第に取り組んだり、逆に重要度の低いタスクに時間を費やしてしまったりします。
理想の職場では?
指示は「具体的+文書化」
ADHDの人が力を発揮できる職場では、以下のような指示を出してもらえると結果を出しやすくなります。
悪い例: 「来週までに資料を作っておいて」
良い例: 「〇月〇日(金)17時までに、A4で5ページ程度の提案資料を作成してください。フォントはメイリオ12pt、余白は上下左右25mm、図表は最低3つ以上含めてください。完成したらメールで送付し、印刷版を10部用意して会議室に持参してください。」
ただ、忙しい職場だとなかなかこのような指示を出してもらえないことも多いです。
その時は、ADHDの人はこの粒度の指示を受けれるように自ら聞くようにしましょう。
文書化の重要性
口頭だけの指示だと、ADHDの人は聞き漏らしたり、記憶が曖昧になったりすることがあります。
メールやチャットツールで指示を文書化してもらえることで、何度でも確認でき、不安が軽減されます。
業務の優先度を数字やマトリクスで明示
複数のタスクがある場合、以下のような方法で優先順位を明確にすることで、ADHDの人でも迷わずに業務を進められます。
- 緊急度・重要度マトリクス
- A:緊急かつ重要(最優先)
- B:重要だが緊急ではない(計画的に実施)
- C:緊急だが重要ではない(短時間で処理)
- D:緊急でも重要でもない(後回し)
- 数字による優先順位
- 1:今日中に完了必須
- 2:今週中に完了
- 3:来週までに完了
- 4:時間があるときに対応
もし優先順位の付け方に不安を感じたら、信頼できる同僚や上司に見てもらうようにしましょう。
④自分から積極的にフィードバックを求めやすい環境

ADHDの人には不安を感じやすい特性があります。自分から進捗報告や相談を積極的にできる環境があることで、安心して業務に取り組めます。

今の職場だと、何か月も上司と話すことがなくて、自分の仕事が正しいのか、評価されているのかが全然わからないんです。でも、忙しそうな上司に自分から声をかけるのも気が引けて…。

その気持ち、とてもよく分かります。ADHDの人は不安を感じやすく、かつ『迷惑をかけているかも』という心配から、なかなか相談できないことが多いんです。でも、自分から積極的にコミュニケーションを取れる環境かどうかは、働きやすさを左右する重要な要素です。
自分から動きやすい職場の特徴
定期的な報告・相談の機会が制度として確立されている
理想的な職場では、1on1ミーティングや定期面談などが制度として設けられています。これにより、「相談したいことがあるんですが…」と切り出す必要がなく、自然な流れで状況を共有できます。
メリットとして
「気軽に相談して」の雰囲気が本当にある
口では「何でも相談して」と言いながら、実際には忙しそうにしていたり、相談すると面倒そうな顔をされたりする職場もあります。本当に相談しやすい職場では
ADHDの特性を活かした積極的なコミュニケーション術
事前準備で相談のハードルを下げる
ADHDの人は、その場で考えをまとめるのが苦手な場合があります。相談前に以下のような準備をすることで、より効果的なコミュニケーションが可能になります。
小まめな進捗報告を習慣化する
大きな問題になってから相談するのではなく、定期的に進捗を報告することで、問題の早期発見・解決が可能になります。
「わからない」を恥ずかしがらない文化
ADHDの人は完璧主義的な傾向があり、「こんなことを聞いたら恥ずかしい」と思いがちです。しかし、早めに確認することで大きなミスを防げることを理解し、積極的に質問できる職場環境が重要です。
効果的な質問の仕方
⑤ ADHDに理解のある上司・同僚の存在

ADHDへの理解と配慮がある職場環境は、当事者が能力を最大限発揮するための最も重要な要素の一つです。

ADHDのことを職場で話すのは勇気がいるんですが、理解してもらえる職場とそうでない職場の違いって何でしょうか?

とても大切な質問ですね。私も最初は打ち明けるのに勇気が必要でした。でも、理解のある職場では、ADHDを「個性」として受け入れ、それを活かそうとしてくれるんです。具体的な特徴をお話しします。
心理的安全性の確保
特性について話せる環境
理解のある職場では、ADHDであることをオープンにしても、以下のような反応が返ってきます
逆に、理解のない職場では
このような反応の違いは、職場の文化や価値観を如実に表しています。
ミスが責められず、解決に向かう文化
ADHDの人は、注意力の問題からミスをしてしまうことがあります。理解のある職場では、ミスそのものを責めるのではなく、なぜそのミスが起こったのか、どうすれば防げるのかを一緒に考えてくれます。
建設的なアプローチの例
「今回のミスの原因を一緒に分析してみましょう。チェックリストを作ったり、ダブルチェックの仕組みを導入したりすれば防げそうですね。」
ダイバーシティが根付いた企業文化
「普通」に合わせるのではなく、「違い」を尊重する
多様性を重視する職場では、以下のような考え方が根付いています。
ADHDの強みを活かす機会の提供
理解のある職場では、ADHDの特性を以下のような強みとして捉えてくれます。
そして、これらの強みを活かせる業務や役割を積極的に任せてくれます。
具体的な配慮の例
自分に合っている職業が分からなければ「3分」で見直してみましょう
現在、働いているが「本当にやりたいことが分からない」「自分はこの仕事に適しているのだろうか」と悩んでいる人も多いと思います。
そのような人は「ココシロ!適職診断![]() 」を受けてみましょう。
」を受けてみましょう。
ココシロ!適職診断![]() は簡単な30個の質問に答えるだけで、あなたの強みや仕事の適正もスグにわかる完全無料の診断サイトです。
は簡単な30個の質問に答えるだけで、あなたの強みや仕事の適正もスグにわかる完全無料の診断サイトです。
最短3分で、あなたの性格や価値観、適職タイプなど一目でわかります。
ADHDの人は自己理解が低く、自分の働き方やキャリアの選択を間違えている場合も多いので、一度利用されることをお勧めします。
詳細は以下よりご覧ください👇👇👇
まとめ:自分に合う環境は必ずある


今日教えてもらった5つの特徴、どれも今の職場にはないものばかりです…。こんな理想的な職場、本当に存在するんでしょうか?

確かに、すべての条件を満たす完璧な職場を見つけるのは難しいかもしれません。でも、これらの特徴のうち、いくつかでも当てはまる職場なら必ず存在します。大切なのは、完璧を求めすぎないことです。
ADHDの人にとって「働きやすい職場」は、決して特別なものではありません。
今回紹介した5つの特徴——フレキシブルな勤務体制、静かで刺激の少ない環境、明確な指示と優先順位、こまめなフィードバック、理解のある人間関係——これらは、多くの職場で実現可能な配慮です。
重要なのは、これらの条件をすべて満たす職場を探すことではなく、自分にとって最も重要な要素が何かを理解し、それを優先的に満たしてくれる職場を見つけることです。
例えば、集中力の問題が最も深刻なら、物理環境やフレキシブルな勤務体制を重視する。人間関係での不安が大きいなら、理解のある上司や同僚がいる職場を優先する。
このように、自分の特性と照らし合わせて優先順位をつけることが大切です。
また、転職だけが解決策ではありません。
現在の職場でも、上司に相談したり、人事部門に働きかけたりすることで、環境を改善できる可能性があります。
ADHDへの理解が広がっている今、多くの企業が多様性への配慮を重視するようになっています。
小さな配慮と理解のある環境があれば、ADHDの人も自分の力を十分に発揮できる場所はきっと見つかります。完璧でなくても、改善しようとする姿勢のある職場なら、そこで成長していくことは十分に可能です。
最後に、ADHDの特性は決して欠点ではなく、適切な環境で活かすことができる貴重な個性だということを忘れないでください。あなたの創造性、集中力、独特の視点は、必要としている職場が必ずあります。
自分らしく働ける環境を見つけるための第一歩として、まずは自分の特性と向き合い、どのような環境なら力を発揮できるのかを整理してみてください。そして、勇気を持って一歩を踏み出してみてください。
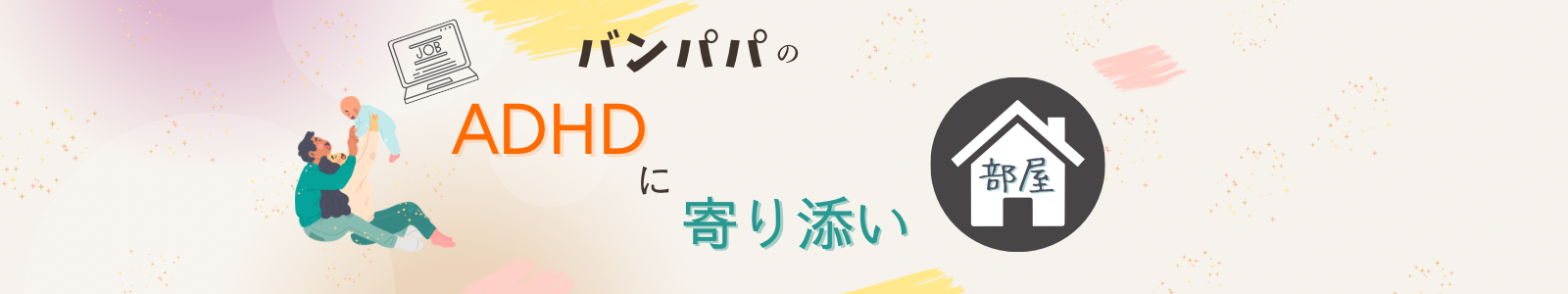





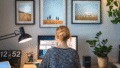
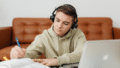
コメント