はじめに|ADHDの人は頭の中がごちゃごちゃで動けない


いつも「あれもやらなきゃ、これもやらなきゃ」って頭がいっぱいになって、結局何も手につかないんです。考えれば考えるほど混乱して…

ADHD傾向のある方は、たくさんのことを同時に考えてしまうので、頭の中が『やることリスト』でいっぱいになってしまうんですよね。でも、そんな時こそ『なぜ?』を使って、本当に大切なことを見つけることができるんです。今日はその方法をお伝えしますね
あなたはこんな経験、ありませんか?
- 「やることがたくさんあって、何から手をつけていいかわからない」
- 「考えれば考えるほど、頭がぐちゃぐちゃになる」
- 「結局、重要なことを後回しにしてしまう」
これらの悩みの根本にあるのは、「What(何をするか)」ばかりに注目してしまい、「Why(なぜするのか)」が見えなくなってしまうことです。
ADHD傾向のある方は、アイデアや気づきがたくさん浮かぶ素晴らしい能力を持っています。
ADHD傾向のある方は、「同時にいろんなことを考えられる」という強みがある反面、それが頭の中で“やることリストの洪水”になってしまうことがあります。
今回の記事はADHDの人が「What(こと)」から「Why(なぜ)」という思考を持つ重要性と実践方法についてご紹介します。
ADHDの思考パターン:Whatの点在とそれによる混乱が生じる

「What」が次々と浮かぶ特性
ADHD傾向のある方の頭の中では、常にたくさんの「What(何をするか)」が浮かんでいます。
例えば、朝起きた時
- 「メールチェックしなきゃ」
- 「洗濯物を畳まなきゃ」
- 「資料作成もある」
- 「友人に返事もしなきゃ」
- 「部屋の掃除も…」
- 「あ、そういえば買い物も」
このように、次から次へと「やること」が浮かんでくるため、頭の中が常に忙しい状態になってしまいます。
深掘りよりも広がる思考
ADHD傾向のある方の思考は、一つのことを深く掘り下げるのが苦手と言われています。
実際には頭の中で、関連することがどんどん広がっていく特徴があります。
例えば 「仕事の資料作成」
→「そういえば昨日の会議の件も」
→「あの件で○○さんに連絡を」
→「○○さんといえば、今度の飲み会の件も」
→「飲み会の場所を調べなきゃ」
このように、一つのことから連想がどんどん広がって、気がつくと最初に考えていたことから遠く離れてしまうのです。
思考が混乱してしまう状態
「What」が点在し、それぞれが関連し合って広がっていくと、頭の中は混乱状態になってしまいます。
この状態では、行動を起こすことがとても困難になってしまいます。
なぜなぜ分析(5why分析)とは:目的を明確にする思考整理術
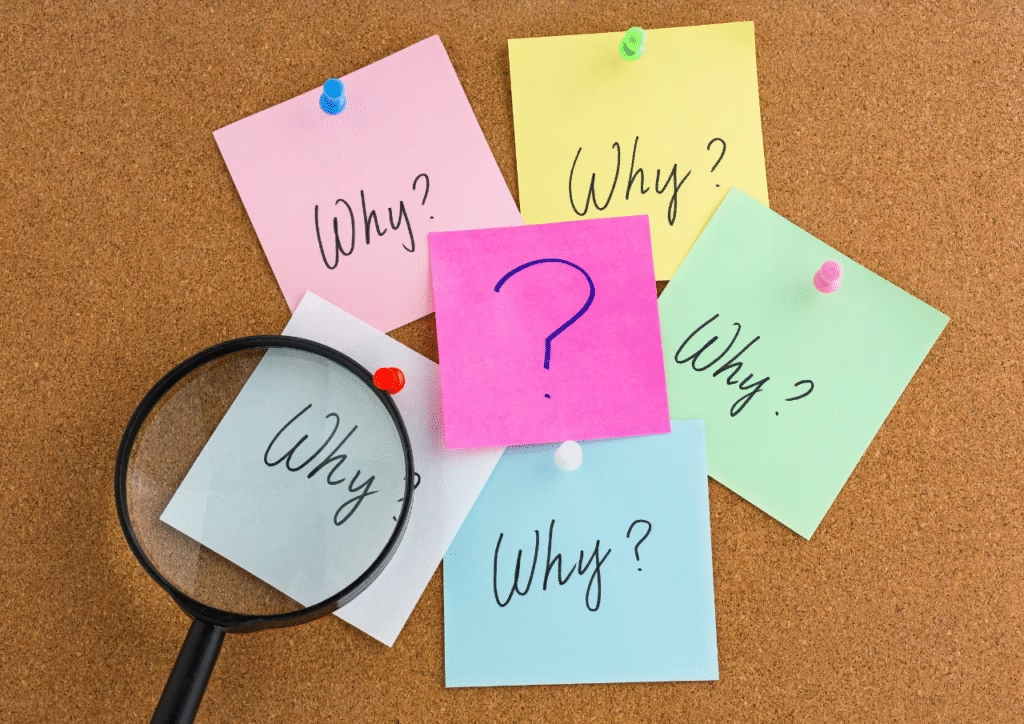
なぜなぜ分析(5why分析)の基本的な考え方
なぜなぜ分析(5why分析)は、名の通り「なぜそれをするのか?」を繰り返し問うことで、本当の目的を明確にする手法です。
ポイントは、「What(何をするか)」から「Why(なぜするのか)」へ視点を変えることです。
ADHD傾向のある方になぜ有効なのか?
1. 思考の方向性を定める
「なぜ?」という質問は、拡散しがちな思考に方向性を与えます。あちこちに飛んでいた考えを、一つの軸に沿って整理することができます。
2. 優先順位が見えてくる
「なぜそれをするのか?」を考えることで、その行動の重要度が明確になります。本当に必要なことと、そうでないことの区別がつきやすくなります。
3. 行動の動機が明確になる
「Why」が明確になると、「やらなければならない」から「やりたい」に気持ちが変わります。これにより、行動へのエネルギーが生まれます。
4. シンプルで覚えやすい
複雑な手法ではなく、「なぜ?」を繰り返すだけなので、覚えやすく実践しやすいのが特徴です。
なぜなぜ分析(5why分析)を使って思考を整理する手順

なぜなぜ分析(5why分析)とは、「なぜ?」を5回繰り返すことで、本当に大切なことや根本原因に気づくための思考法です。では、実際にどのような手順で行えばいいのでしょうか?
ステップ1:今抱えているモヤモヤや悩みを1つ書き出す
頭の中にある「What(やること)」の中から、一番気になるものを選びます
ステップ2:それに対して「なぜ?」と問いを立てる
「なぜそれが気になるのか?」「なぜそれをしたいのか?」を考えます
ステップ3:それに対する答えを出す
思いつく理由を素直に書き出します。正解を求めず、今感じていることを書きましょう
ステップ4:さらにその答えに対して「なぜ?」と問いを重ねる(×5回)
答えに対してさらに「なぜ?」を繰り返します
ステップ5:最終的に残った答えが、あなたの「本音」や「価値観」のヒント
5回目の「なぜ?」で見えてきたものが、本当に大切にしていることです
実際になぜなぜ分析(5why分析)を使ってみると、こんなふうに「表面的な悩み」から「本当の原因」までたどり着けます。以下はその一例です。
実際にやってみた例【モヤモヤ→スッキリまでの5段階】
例1:やることが多すぎて手がつけられない…
1. なぜやることが多すぎると感じるの? → どれも手をつけられなくてパニックになるから
2. なぜ手をつけられないの? → どれから始めればいいか分からないから
3. なぜ優先順位がつけられないの? → どれも「やらなきゃ」と思ってしまっているから
4. なぜ全部「やらなきゃ」と思うの? → 周囲に迷惑をかけたくない・完璧にやりたいから
5. なぜ完璧にこだわってしまうの? → 自分に自信がないから
結果:「優先順位がつけられない」のではなく、「自信のなさ」が根底にあった! → まずは「完璧主義の手放し」から始めよう。
例2:朝起きられなくて困っている
1. なぜ朝起きられないの? → 夜更かしをしてしまうから
2. なぜ夜更かしをしてしまうの? → 夜の時間が唯一の自分時間だから
3. なぜ自分時間が必要なの? → 日中は人に気を使って疲れるから
4. なぜ人に気を使って疲れるの? → 嫌われたくないから
5. なぜ嫌われたくないの? → 一人ぼっちになるのが怖いから
結果:「早寝早起き」の問題ではなく、「人間関係の不安」が根本原因だった! → 安心できる人間関係作りから始めよう。
例3:仕事でミスばかりしてしまう
1. なぜミスばかりしてしまうの? → 集中力が続かないから
2. なぜ集中力が続かないの? → 他のことが気になってしまうから
3. なぜ他のことが気になるの? → 「これも忘れちゃいけない」と思うから
4. なぜ忘れちゃいけないと思うの? → 迷惑をかけたくないから
5. なぜ迷惑をかけたくないの? → 役に立たない人だと思われたくないから
結果:「集中力の問題」ではなく、「自己価値の不安」が根本原因だった! → 自分の価値を認める練習から始めよう。
このようにWhy分析を使うと、単なる「やることが多い」悩みから、自分の深い思いが浮かび上がってきます。表面的な問題の奥にある、本当の気持ちや価値観に気づくことができるのです。
なぜなぜ分析(5why分析)を習慣化する方法
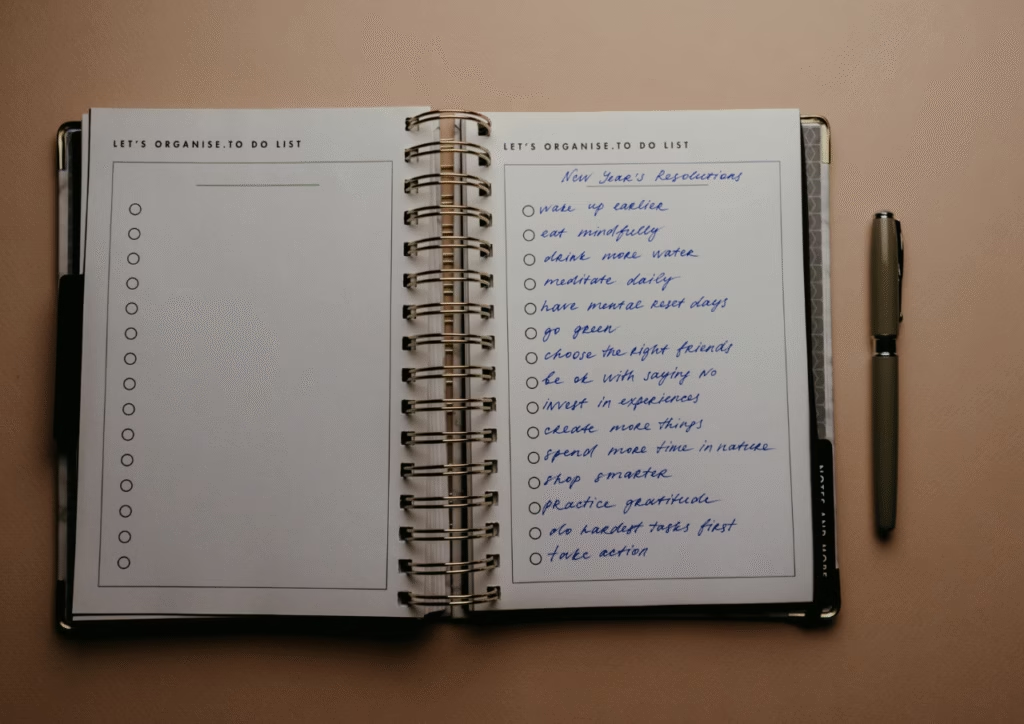
いわゆる「Why型思考」は毎日のちょっとしたステップを踏むことで身に付けることができるので、ぜひ実践してみてください。
ステップ1:1日5分から始める
最初は大きな問題ではなく、日常の小さな困りごとから始めましょう。
おすすめのタイミング
- 朝、その日の予定を立てる前
- 夜、一日を振り返る時
- 何かに迷った時、その場で
ステップ2:書き出すことから始める
頭の中だけで考えると、またWhatが拡散してしまいます。紙やスマホのメモ機能を使って、必ず書き出しましょう。
今気になっていること:
選んだもの:
なぜ1:
なぜ2:
なぜ3:
なぜ4:
なぜ5:
分かったこと:
ステップ3:完璧を求めない
5回まで行かなくても、途中で「あ、これが理由だ!」と気づいたら、そこで止めても大丈夫です。大切なのは、「Why」を考える習慣をつけることです。
ステップ4:デジタルツールの活用
スマホのメモアプリ
- いつでもどこでも使える
- 音声入力で素早く記録
- 過去の分析結果を検索可能
- テンプレートを作成して効率化
- 日付やタグで整理
- 振り返りがしやすい
マインドマップ
- 視覚的に整理できる
- 関連性が見えやすい
- 色分けで優先度を表現
マインドマップに関する紹介記事はこちら👇
なぜなぜ分析で変わる日常生活

ADHDの人がなぜなぜ分析(5why分析)を用いることで日々の生活が劇的に変わります。 そして「何歳から」でも変わることができるのです。
迷いが減る
何かを選択する時、「なぜそれを選ぶのか?」を考える習慣がつくことで、迷う時間が大幅に減ります。目的が明確になれば、選択は自然と決まります。
集中力が向上する
「なぜこれをするのか?」が明確になることで、その行動に対する集中力が格段に向上します。義務感ではなく、目的意識を持って取り組めるようになります。
自己理解が深まる
継続的にWhy分析を行うことで、自分が本当に大切にしていることが見えてきます。これにより、自分に合った環境や仕事を選びやすくなります。
ストレスが軽減される
「やらなければならない」ことが「やりたいこと」に変わることで、日常のストレスが大幅に軽減されます。
なぜなぜ分析(5why分析)の次のステップ:どう活用すればいいの?

なぜなぜ分析(5why分析)で自分の価値観や本音に気づいたものの、 「で、これって実生活でどう活かせばいいの?」 と感じた方もいるかもしれません。
ここでは、Why思考を現実の行動につなげるためのステップを紹介します。
ステップ1:自己分析の深堀り
まず、 なぜなぜ分析で出てきた「自分らしさ」や「本音」を、さらに言語化・整理するプロセスを踏みます
自己分析ノートやジャーナリング性格診断ツール
なぜなぜ分析(5why分析)で見えてきた自分の価値観や動機を、より体系的に理解するために、性格診断ツールを活用してみましょう。
エニアグラム
9つの性格タイプから自分の基本的な動機や恐れを理解できます。なぜなぜ分析(5why分析)で見つけた「なぜ」の背景にある、より深い動機を知ることができます。
ストレングスファインダー
自分の才能や強みを客観的に把握できます。なぜなぜ分析(5why分析)で明確になった目的を達成するために、どの強みを活かせばいいかが分かります。
Step2:相談してみる・他者の視点を取り入れる
一人で考えすぎず、外部のフィードバックを得ることで、より行動につながります。
ADHD特性を理解したキャリアコーチ
一般的なキャリア相談だけでなく、ADHD傾向のある方の特性を理解したプロに相談することで、より適切なアドバイスを受けることができます。
ピアサポートグループ
同じような特性を持つ仲間との交流は、Why分析で得た気づきを共有し、さらに深い理解につながります。
Step3:「自分のWhy」が活かせる場所を見つける
「自分にとって意味がある」「価値観に合っている」といった気付きを得た後、何かしらの行動を取りたくなるのは、なぜなぜ分析のおかげです。
その実践の場として最も気軽に始めやすいのが「副業」と言われています。
なぜなぜ分析 × 副業:なぜ相性が良いのか?
なぜなぜ分析は本業で活きるというのは、今まで上げてきた内容で分かると思います。
ではなぜ副業と相性が良いのか、それは以下が挙げられます。
このように自分らしく生きるためには、なぜなぜ分析と副業を組み合わせることが最適なのです。
自分の「Why」を活かせる副業
なぜなぜ分析(5why分析)で明確になった自分の価値観や目的を活かせる副業に挑戦することで、さらに自己理解を深めることができます。
クリエイティブ系
- ライティング
- デザイン
- 動画制作
- イラスト制作
分析・コンサルティング系
- データ分析
- 業務効率化支援
- SNS運用代行
- オンライン講師
自分の特性を活かせる副業を探している方、自分の特性が分からないという方は「マンツーマンの副業サポート【スキルコンシェルジュ】」というサービスを使ってみましょう。
「マンツーマンの副業サポート【スキルコンシェルジュ】」では様々な副業を経験してきた現役のフリーランスが性格や得意な事などからぴったりの副業をご提案してくれます。さらに各副業のプロがマンツーマンでサポート。
まずは「無料」で相談してみませんか。
詳しくはこちら👇
併せて以下のブログ記事でも副業についてご紹介していますので、ぜひご覧ください👇
まとめ:「なぜ?」で見つける本当の目的

なぜなぜ分析をやってみて、自分が本当にやりたいことが見えてきました!でも、これを毎日続けるのは大変そうで…

毎日できなくても全然大丈夫ですよ!大切なのは、迷った時や頭がごちゃごちゃになった時に、『なぜ?』を思い出すことです。それだけでも、きっと今までとは違う視点で物事を見られるようになります。あなたの『たくさん考える』特性は、実は『たくさんの可能性を見つける』素晴らしい能力なんです。Why分析で、その可能性を整理して、本当に大切なものを見つけてくださいね
ADHD傾向のある方の頭の中は、いつもたくさんの「What(やること)」でいっぱいです。でも、それは決して悪いことではありません。多くの可能性を同時に考えられる、とても豊かな能力なのです。
ただ、その豊かさを活かすためには、「Why(なぜ)」という軸で整理することが大切です。Why分析は、そのための最もシンプルで効果的な方法です。
「なぜ?」を5回繰り返すだけで、頭の中の混沌とした「What」が、明確な目的を持った行動に変わります。そして、その目的が明確になった時、あなたは今までとは違う集中力と行動力を発揮できるようになるでしょう。
今日から、迷った時や頭がごちゃごちゃになった時は、ぜひ「なぜ?」を思い出してください。きっと、あなたの中に眠っている本当の目的が見つかるはずです。
そして、その目的に向かって進んでいく中で、あなたらしい働き方や生き方も見えてくるでしょう。ADHD傾向のある方の特性は、適切な環境で発揮されれば、大きな強みとなります。
あなたの「考える力」を信じて、一歩ずつ前進していきましょう。
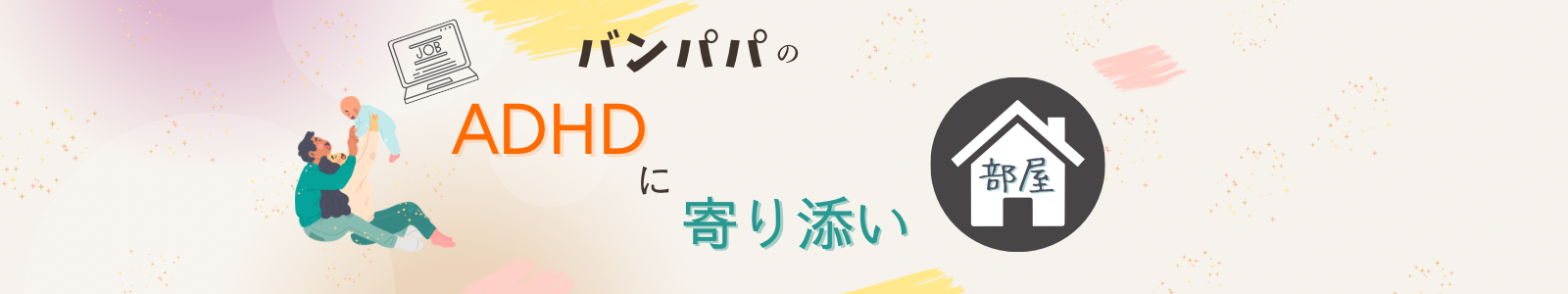
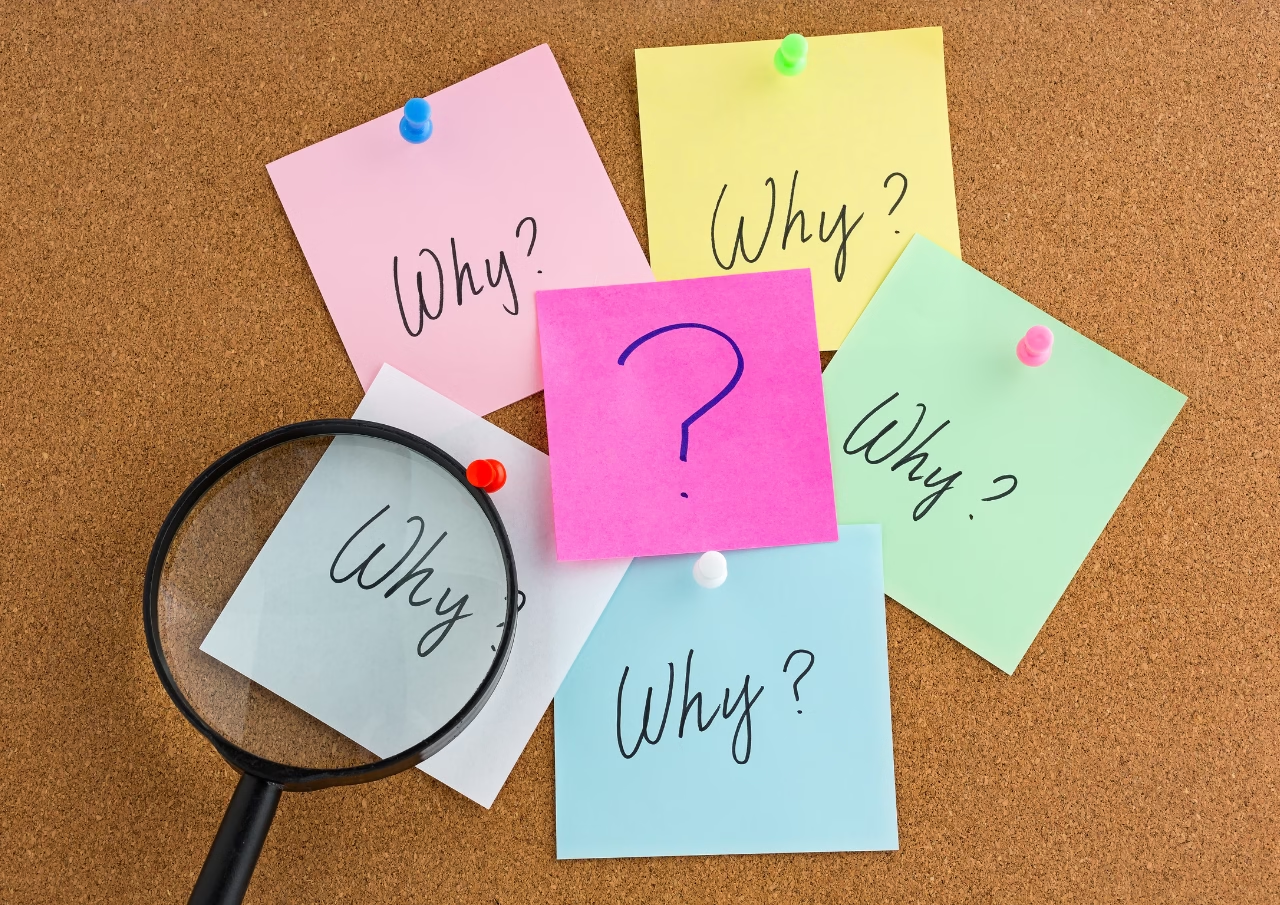





コメント