はじめに

ADHD(注意欠如・多動性障害)の人は人間関係で悩むことが多いと言われています。
具体的にはなぜか特定のタイプの人といると異常に疲れてしまったり、集中力がガクッと落ちたり、自分に自信がなくなってしまったり。
そんな経験、ありませんか?
実は、これらには明確な理由があります。ADHD当事者の脳の働き方と相手の行動パターンが合わないことで起こってしまう現象です。
この記事は、ADHD当事者である僕自身の体験と、たくさんの専門書で得た知識をベースに書いています。同じような悩みを持つ皆さんにとって、少しでも役立つ情報になれば嬉しいです。
この記事で得られること
1.自分の感情や反応が理解できる
「なぜあの人といると疲れるんだろう」「どうして集中できなくなるんだろう」といった、今まで何となく感じていた不快感の正体がはっきりしてきます。これで、自分を責めることなく冷静に状況を見ることができるようになります。
2. 実際に使える対処法がわかる
苦手なタイプの人との関わりを完全に避けるのは無理ですが、ストレスを最小限に抑える具体的な方法をお伝えします。職場や家庭での人間関係が改善して、日常生活がもっと楽になるはずです。
3. 自分を守るスキルが身につく
ADHD当事者として自分を守りながら、健全な人間関係を築く方法をお教えします。これで、自分に自信が持てるようになり、精神的にも安定してきます。
4. 本当に大切なことにエネルギーを使えるようになる
苦手な人との関わりで消耗していたエネルギーを、本当に大切なことや自分の成長のために使えるようになります。結果として、もっと充実した人生を送れるようになります。
5. 自分のADHD特性との付き合い方が上手になる
自分のADHDの特性をより深く理解することで、得意なことを活かして、苦手なことをカバーする生活スタイルが作れるようになります。
ADHDとは?知っておきたい基本情報

ADHD(注意欠如・多動性障害)は、集中するのが難しい、落ち着きがない、衝動的な行動を取りやすいといった特徴を持つ発達障害の一つです。最近、大人になってからADHDと診断される人が増えていて、社会的にも知られるようになってきました。
ADHD脳の3つの特徴
ADHDには、主に以下の3つの特徴があり、これらが複合的に現れることが多いです。
集中力の波が激しい(不注意症状)
- 物事に集中し続けることができない
- 細かいところに注意を向けるのが苦手
- 忘れ物や無くし物が頻繁に起こる
- 話や説明を聞き逃すことが多い
- 作業や活動を最後まで完了させるのが難しい
- 時間の管理や優先順位をつけるのが苦手

私は会議中に上司の話を聞いてるつもりでも、気づいたら別のことに意識が飛んでしまいます。
で、急に「○○さん、どう思う?」って振られて「えっ?」となり、答えたことが的外れなことも…。
体がソワソワする(多動症状)
- 長時間じっとしているのがつらい(足が無性にムズムズする)
- 手足をそわそわと動かしてしまう
- 会議や授業中に席を立ちたくなる
- 内側で落ち着かない感じがする
- エネルギーがありすぎて疲れを感じにくい

単純作業や単調なデスクワークが本当にしんどくて、気づくとペンをカチカチやってたり、足をゆらゆらしてたり。
同僚や家族には「落ち着きないね」ってよく言われます。
思いつきで行動しちゃう(衝動症状)
- 考えるより先に行動してしまう
- 会話で相手の話を最後まで聞けずに口を挟んでしまう
- 買い物の衝動をコントロールするのが難しい
- 怒りやイライラをすぐに表に出してしまう
- 計画を途中で変更したくなる

これで何度失敗したことか…。特に人間関係では「なんで今それ言っちゃったんだろう」って後悔することが多すぎます。
※これらの症状は、年齢や生活環境、ストレスの度合いによって出方が変わりますし、人によっても大きく違います。
なぜADHDになるの?|脳科学から見た原因
最新の研究では、ADHD脳は前頭前野という「司令塔」の部分の発達がゆっくりだったり、ドーパミンという「やる気ホルモン」の分泌が少なかったりすることがわかってます。
脳の構造と働きの違い
- 前頭前野の発達が遅れたり活動が低下している
- 線条体や小脳の神経回路の成熟度が違う
- 脳内の神経伝達物質(ドーパミン、ノルアドレナリン)の分泌や受け取り方に問題がある
遺伝的な要因
- 家族内でADHDの人が多い傾向がある
- 特定の遺伝子の変化との関連がある
環境的な要因
- 妊娠中の母親の喫煙や飲酒
- 早産や低出生体重
- 小さい頃の頭のケガや感染症
これらの要因が重なり合って、ADHDの症状が現れると考えられています。
ADHD当事者の日常生活|リアルな困りごと
ADHDを持つ人は、その特性によって日常生活のいろいろな場面で困難を経験します。これらの困難は、単なる「性格の問題」ではなく、脳の働き方の違いによるものです。
仕事での困りごと
- 長時間の会議や単調な作業に集中できない
- 締切の管理や優先順位の判断が難しい
- 同僚とのコミュニケーションでトラブルが起きやすい
- 細かいミスが多くなって、品質に影響が出る
- 新しい仕事を覚えるのに時間がかかる
プライベートでの困りごと
- 友達との約束の時間を忘れて、待ち合わせ場所で慌てて連絡
- 家事を始めても途中で他のことが気になって中断
- 衝動買いで家計がピンチになることも…
- 部屋が汚すぎて人を呼べない
- 大事な書類をどこに置いたか分からなくなる
勉強での困りごと
- 授業に集中し続けることができない
- ノートを取りながら話を聞くのが難しい
- 宿題や課題の管理ができない
- 試験勉強の計画を立てて実行するのが苦手
- グループワークでの協調性に問題がある
家庭・私生活での困りごと
- 家事の段取りや継続が難しい
- お金の管理や家計の把握が苦手
- 家族との約束を忘れてしまう
- 物の整理整頓ができない
- 時間の感覚があいまいで遅刻が多い
人間関係での困りごと
- 相手の話を最後まで聞けずに誤解を招く
- 感情のコントロールが難しくて衝突しやすい
- 約束を忘れて信頼を失う
- 空気を読むのが苦手で場違いな発言をしてしまう
これらの困りごとは、周りの理解不足によって「怠けている」「やる気がない」と誤解されることが多く、ADHD当事者にとって大きなストレスになります。
そして、周囲の適切な理解と支援があれば、多くの困りごとは軽くなることがわかっています。
大人ADHDの特徴については以下の記事でも紹介しております👇

ADHDの人が苦手とする人の特徴

前章まではADHDの特徴や困りごとを挙げてきました。ADHDは第三者から「一般的な人とはずれている(一般的な考えとは違う)」と思われることも多々あります。
この章では実際に生活するうえで、ADHD当事者として長年生活してきた経験から、特に苦手に感じる人のタイプ(相性が良くない人)を挙げていきます。
これらの人々との関わりは、私たちの症状を悪くして、日常生活に大きなストレスをもたらすので、参考にしてみましょう。
1. 早口で話が途切れない人
なぜ苦手なのか
ADHD当事者にとって、早口でどんどん話す人との会話は、まさに情報処理能力の限界を超える体験です。僕たちの脳は、一度にたくさんの情報を処理するのが苦手で、特に耳から入る情報が高速で流れ込むと、脳がパンクしてしまいます。
具体的な困り事
- 話の内容を理解する前に次の話題に移ってしまう
- 重要なポイントを聞き逃してしまい、後で困る
- 質問したいことがあっても、話の隙間がなくて割り込めない
- 会話についていけず、だんだんと集中力が切れてしまう
- 相手に「ちゃんと聞いているの?」と言われてさらにストレスが増す
対処法
このタイプの人とは、できるだけ1対1での長時間の会話を避け、メールやチャットなど文字でのやり取りを提案するのが効果的です。
どうしても直接話さなければならない場合は、「もう少しゆっくり話していただけませんか?」と正直にお願いするか、「重要な点をメモしたいので、少し待ってください」と間を作ることが大切です。
2. 細かい指示やルールにこだわる人
なぜ苦手なのか
ADHD当事者は、全体像を把握してから詳細に入るという考え方をします。
しかし、細かいルールや手順にこだわる人は、まず細かいところから入り、それらを厳密に守ることを要求します。この考え方の違いが、大きなストレスと混乱を生み出します。
具体的な困り事
- 手順書通りに作業することに集中しすぎて、目的を見失ってしまう
- 細かいルールを覚えきれずに、何度も同じ指摘を受ける
- 工夫や効率化を提案しても「ルールだから」で片付けられる
- ミスを指摘されるたびに自分への信頼がなくなる
- 「なぜそのルールが必要なのか」の説明がないと納得できない
対処法
このタイプの人とは、最初に「なぜそのルールが必要なのか」を確認し、全体の目的を共有してもらうことが重要です。また、チェックリストを作成して目で見て確認できるようにしたり、作業を小分けにして段階的に進める方法を提案しましょう。
3. 変化を嫌う人
なぜ苦手なのか
ADHD当事者の多くは、新しいことを求める気持ちが強く、新しいことに挑戦したり、変化を楽しんだりすることを好みます。
一方、変化を嫌う人は、今までのやり方や環境を維持することを重視するため、価値観の根本的な違いが生じます。
具体的な困り事
- 新しいアイデアや改善提案を頭ごなしに否定される
- 「今まで通りで問題ない」という理由で成長の機会を失う
- 刺激の少ない環境では集中力が維持しにくい
- 創造性や柔軟性を発揮する機会が制限される
- 変化への適応力というADHDの良さを活かせない
対処法
変化を嫌う人との関係では、小さな変化から始めて徐々に慣れてもらう戦略が有効です。また、変化のメリットを具体的な数字や事例で示し、リスクを最小限に抑える計画を一緒に立てることで、理解を得やすくなります。
4. 要求が曖昧な人
なぜ苦手なのか
ADHD当事者は、抽象的な指示よりも具体的ではっきりした指示を好みます。あいまいな要求は、何から手をつけて良いかわからず、混乱と不安を引き起こします。また、完了の基準が不明確だと、いつまでも作業が終わらない感覚に陥ります。
具体的な困りごと
- 「適当に」「なんとなく」「いい感じに」といった指示では何をすべきかわからない
- 完成のイメージが共有されないため、何度もやり直しが発生する
- 「もっと工夫して」「センス良く」など感覚的な指示に困惑する
- 期待値がわからず、結果的に相手を失望させてしまう
- 自分なりに頑張っても「そうじゃない」と言われて自信を失う
対処法
あいまいな指示を受けた時は、恥ずかしがらずに具体的な確認を取ることが重要です。「具体的にはどのような内容でしょうか?」「完成のイメージを教えてください」「参考になる資料はありますか?」といった質問を積極的に行いましょう。
5. 過去の失敗を責める人
なぜ苦手なのか
ADHD当事者は、その特性上ミスをしやすい傾向があります。過去の失敗を繰り返し責められることは、ただでさえ低い自分への信頼をさらに下げ、うつ状態や不安障害を併発するリスクを高めます。
具体的な困りごと
- 同じ失敗を繰り返すことへの恐怖で萎縮してしまう
- 新しいことに挑戦する意欲を失う
- 完璧主義に陥り、逆に作業効率が下がる
- 自己批判が強くなり、メンタルヘルスに悪影響
- 「また失敗するかも」という不安で集中力が低下する
対処法
このタイプの人とは、距離を置くことが最も重要です。もし職場の上司などで避けられない場合は、失敗した時の対処法を事前に決めておく、ミスを防ぐためのシステムを構築する、第三者に相談するなどの対策を講じましょう。
ADHDは職場環境を変えることも大切
ADHDはいる環境から変わることを恐れ、現状から目を反らしてしまいがち。結果として自分を苦しめてしまいます。
詳細は以下の記事でもご紹介しています👇

この状態を避けるために、ADHDに職場の人間関係で悩みを抱えている方は、ADHDに理解のある職場への転職を検討してみてはいかがでしょうか。
特に障害者雇用に特化した転職エージェントでは、あなたの特性を理解し、適した職場を紹介してくれます。

でもADHDに関してちゃんと理解してくれる人なんているのでしょうか。

大丈夫です。採用大手のパーソルダイバース株式会社が運営しているdodaチャレンジは一人ひとりに寄り添った転職支援をサポートしてくれます。
ADHDの人は人や働く環境によって仕事の出来も左右されてしまいます。その時は一度、ADHDに理解を持っているプロに相談してみるのも一つの方法です。
特にお勧めなのが「障害者雇用に特化した転職エージェント」大手のパーソルダイバース株式会社が運営しているdodaチャレンジ。
一人で悩まず「働き方のプロ」に相談してみることで今後の働き方のヒントにつながります。
詳しくは以下サイトもご覧ください↓↓
なぜADHDの人はこれらのタイプの人を苦手とするのか?
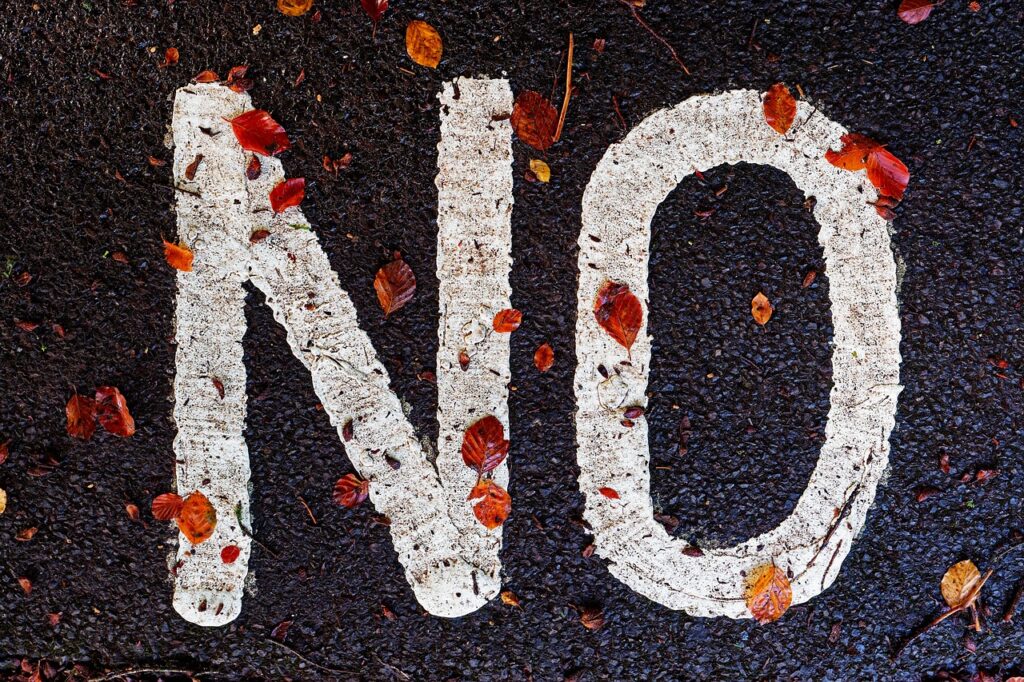
ADHD当事者がこれらのタイプの人を苦手とする理由は、単なる好き嫌いの問題ではありません。脳の構造と働きの違いに基づく、体の自然な反応なのです。
脳科学的な背景
前頭前野の働きの問題
ADHD当事者の前頭前野は、一般的な人と比べて活動が低下していることが多く、以下の働きに影響を与えます。
- 実行機能(計画立案、優先順位付け、作業記憶)
- 注意の制御と維持
- 衝動の抑制
- 感情の調整
神経伝達物質のバランスの問題
ドーパミンとノルアドレナリンの分泌や受け取り方に問題があり、以下の影響が現れます。
- 注意の集中と維持の困難
- 報酬系の働きの問題による動機の低下
- 新しいことを求める行動の増加
- ストレス反応の過敏化
情報処理の特徴
複数のことを同時に処理するのが苦手
ADHD当事者は、複数の情報を同時に処理することが困難です。早口で話し続ける人や、複雑な指示を一度に出す人との関わりでは、脳が情報過多の状態になり、混乱やパニックを引き起こします。
注意の分散と過集中
注意を適切にコントロールすることが難しく、重要でないことに過度に集中してしまったり、逆に重要なことに注意を向けられなかったりします。細かいルールにこだわる人との関わりでは、ルールに過集中してしまい、本来の目的を見失ってしまいます。
刺激の調整困難
ADHD当事者は、適度な刺激を求める一方で、過度な刺激には耐えられません。変化を嫌う人との関わりでは刺激不足でやる気を失い、逆に過度に批判的な人との関わりでは刺激過多でストレス反応が強くなります。
ストレス反応の違い
ストレスホルモンの過剰分泌
ADHD当事者は、ストレス反応が過敏で、コルチゾールなどのストレスホルモンが過剰に分泌される傾向があります。これにより、以下の症状が悪化します。
- 注意力のさらなる低下
- 記憶力の減退
- 感情の不安定化
- 体調不良
闘争・逃走反応の活性化
苦手なタイプの人との関わりでは、原始的な防衛反応である闘争・逃走反応が活性化し、理性的な思考が困難になります。これが、これらの人から「1秒でも早く離れたい」と感じる理由の一つです。
ADHD当事者が実践できる対処法と自己防衛策

苦手なタイプの人との関わりを完全に避けることは困難ですが、ADHD当事者として長年の経験から学んだ効果的な対処法をご紹介します。
環境を整える
物理的距離を設ける
可能な限り、苦手なタイプの人との物理的距離を保つことが重要です。オフィスでは席を離してもらう、会議では直接向かい合わない位置に座る、休憩時間をずらすなど、小さな工夫が大きな効果をもたらします。
時間的距離を設ける
一度に長時間関わることを避け、短時間の関わりを複数回に分けることで、ストレスを軽減できます。また、苦手な人との関わりの後は、回復時間を設けることが重要です。
コミュニケーション手段を選択する
直接の対話が困難な場合は、メールやチャット、書面でのやり取りを提案しましょう。文字情報は処理しやすく、後で見返すこともできるため、ADHD当事者にとって有利です。
心理的に防ぐ方法を見つける
考え方の見直す
苦手な人の行動を個人攻撃として受け取るのではなく、「この人はこういう特性の人なんだ」と客観視することで、感情的な反応を和らげることができます。
境界線の設定
どこまでが自分の責任で、どこからが相手の責任なのかを明確にし、過度に自分を責めることを避けます。「私はベストを尽くした」「相手の反応は相手の問題」という認識を持つことが大切です。
協力してもらうための関係を構築
信頼できる同僚、友人、家族に状況を相談し、理解と支援を得ることで、孤立感を避けることができます。また、ADHDの当事者会やオンラインコミュニティに参加することも有効です。
具体的な対話技術
ADHDは柔軟なコミュニケーションが苦手なので、自分なりの「型」を見つけてみましょう。
構造化されたコミュニケーション
- 会話の前に目的と時間を明確にする
- 話すポイントを事前にメモしておく
- 理解できなかった点は遠慮なく確認する
- 重要な内容は後でメールで確認する
アサーティブネス(自己主張すること)の実践
- 自分の権利を尊重しつつ、相手の権利も尊重する
- 感情的にならずに事実を伝える
- 「No」と言う権利を行使する
- 代替案を提示する
セルフケアの重要性
ストレス管理
- 定期的な運動や散歩
- 深呼吸や瞑想などのリラックス法
- 十分な睡眠時間の確保
- 好きな音楽を聴く、読書をするなどのリフレッシュ活動
専門的支援の活用
- 心理カウンセリングやコーチングの受講
- 精神科や心療内科での薬物療法の検討
- ADHDの特性に詳しい専門家からのアドバイス
- 職場での合理的配慮の申請
これらの対処法を実践することで、苦手なタイプの人との関わりによるストレスを軽減し、自分らしく生活することが可能になります。
まとめ:自分を守りながら前向きに生きるために
ADHD当事者として、苦手なタイプの人との関わりは避けて通れない現実です。しかし、それらの関係性によって自分らしさを失ったり、持っている能力を発揮できなくなったりする必要はありません。
重要なポイントの再確認
自己理解の深化
自分がなぜ特定のタイプの人を苦手とするのかを理解することで、感情的な反応を客観視し、適切な対処法を選択できるようになります。これは、自分を受け入れることと成長の第一歩です。
環境選択の重要性
可能な限り、自分の特性を理解し、受け入れてくれる環境を選ぶことが重要です。職場選び、住環境、人間関係において、自分にとって健全な環境を優先することは、わがままではなく、必要な自己防衛です。
境界線の設定
他人の問題と自分の問題を分けて考え、過度に責任を負わないことが大切です。ADHD当事者は共感する気持ちが強く、他人の感情に巻き込まれやすい傾向があるため、意識的に境界線を設定する必要があります。
支援の活用
一人で抱え込まず、専門家や理解のある人々からの支援を積極的に活用しましょう。ADHDは個人の努力だけでは解決できない脳の特性であり、適切な支援があれば大幅に改善できます。
前向きな未来へのメッセージ
ADHD当事者には、独創性、創造性、エネルギッシュさ、共感する気持ちなど、多くの素晴らしい特性があります。苦手な人との関わりに悩まされることなく、これらの良さを活かせる環境や人間関係を築くことで、充実した人生を送ることが可能です。
時には距離を置くことも、時には勇気を持って立ち向かうことも必要ですが、最も重要なのは自分自身を大切にし、自分らしく生きることです。この記事が、同じような悩みを持つADHD当事者の皆さんにとって、少しでも参考になれば幸いです。
あなたは一人ではありません。理解し、支援してくれる人々がいることを忘れずに、自分の人生を前向きに歩んでいきましょう。
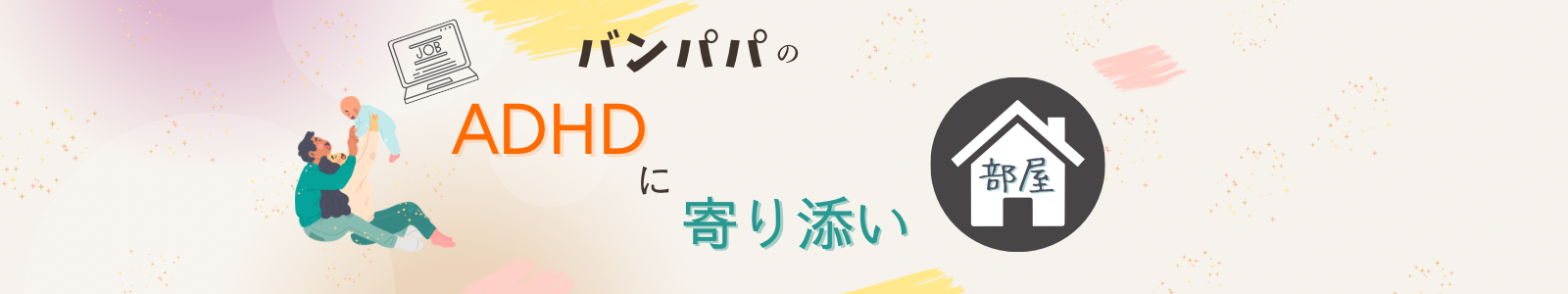




コメント